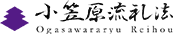







日本の伝統文化には、香、華、茶など、
様々な分野における道があります。
禮(礼)、もそのひとつです。
目に見える所作はもとより、
細やかなこころ遣いまで、
生涯学び続け、
成長することのできる禮の道です。
小笠原流礼法は約700年前、
武家社会において確立され、
今に受け継がれています。
その基本は、
相手を大切に思うこころを
作法というかたちで表し、
人間関係を円滑にする
ということです。
慎み深くうるわしいこころを
持ちながら、
互いのこころを察し、
状況に応じた自然で美しい
ふるまいを学ぶ。
集う人の年齢や環境は異なっても、
学びの空間に生まれる和が
幸せな気持ちへと導く。
それこそが、
私たちの目指す禮の道です。
慌ただしい日常のなかで、
穏やかな時間を
おつくりになりませんか。




小笠原流礼法宗家本部の講義実績は
多岐に渡ります。
小学校、中学校、高等学校、大学、その他各種団体でも指導させていただいております。





小笠原流礼法宗家本部教場(小笠原伯爵邸)、
カルチャースクール、個人教室など
様々な場所でお教室が開かれております。
各教室の様子や、講師についてなどは
こちらをご参照ください。
小笠原流礼法宗家本部の各教室では、
男女問わず幅広い年齢層の方々が学んでいます。
門下生の声をまとめました。







外部コンテンツ
